朝、長女と夫を送り出して、ゆうりにおっぱいをあげると、なみなみとコーヒーを入れて本を読む。
ゆうりの小さくて穏やかな呼吸の音を聞きながら、言葉を味わい、愛でていく。

もう何年も仕事関係以外の本なんて読んでいなかった。
読書の合間にふと目を上げると、窓から空と、雲と、風にゆれている洗濯物が見えて、ものすごい幸福感に包まれる。
ずっとずっと、この時間が続けばいいと願う。

つい数ヶ月前まで、大学病院の一スタッフとしてガムシャラに働いてきたあの日々が、ぼんやりとした夢の中の出来事のように思える。
母はいつも私に言っていた。
「あなたはいつも緊急事態ね。」
いつも忙しくて、いつも何かに追われている。
仕事、子育て、勉強、仕事、タスク、タスク、タスク…
いつも時間が足りなかった。
長女を産んでから、あんなに恋焦がれて、文字通り、死ぬほどがんばって得た助産師という資格。
いつの間にか持っていることが当たり前となり、原動力は情熱や夢や志といったものから、恐怖、不安、焦りへと変わった。
産婦人科病棟には色んな患者さんが出たり入ったり。
何年目になっても、今日は何があるのか、どんな人を看ることになるのか、怖かった。
いつまでたっても、自信をもって、仕事をすることができなかった。
ありとあらゆる勉強会に出席し、休みの日には講習に行き、自分の仕事に対する自信のなさを知識をつけることでカバーしようと必死だった。
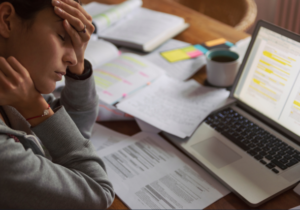
漠然とした焦りと恐怖。
一般のお産は専用の病棟に入院になるため、私が配属された産婦人科病棟は婦人科看護がメインで、たまにある出産は、いわゆる「ハイリスク」と呼ばれる医療行為が必要な方たちがほとんどだった。
予定より随分早く赤ちゃんが生まれそうになっている妊婦さん、血圧がなんだかべらぼうに高くなってしまった人、つわりのレベルを超えて、水も飲めず、脱水になってしまった人、お産のときに出血が止まらなくなってしまった人。何か疾患を合併している人。
子宮筋腫とか、良性の何かをとるために手術をする人。
がんで化学療法中の人、がんの手術をする人、がんと診断される人。亡くなり行く人。
とにかく命を守る、安全を守る、入職して数年間は毎日そのことに必死になりながら働いていた。
新人のころ:初めて死に向かう人を看護すること
2年目頃だったか、入職してしばらくした頃、初めてターミナルの患者さんを受け持った。
全身に広がったがんが肺にも転移し、どんな薬を使っても、どんなに酸素を使っても、彼女の呼吸は日に日に苦しくなっていった。
ある日、午前中のケアを終えて廊下に出ると、実母に鋭く呼び止められた。
どうして何もしてくれないのか、
他にできる治療はないのか、
あんなにあんなに苦しそうなのに、まだあんなにも若いのに。
実母は悲痛の涙を流しながら、私に憎しみをぶつけた。
私には何一つ返す言葉がなくて、何か一言でも発したら、泣いてしまいそうで、ただただ両手を握ってじっと俯いていると、空気に気付いた先輩が私のPHSを鳴らしてNSステーションに呼び戻してくれた。
「もりたさんは何も悪くないんだよ。やりきれない思いをどこにもぶつけられない家族は、それをそのままスタッフや先生にぶつけることがあるんだよ。」
やさしく諭してくれる先輩の言葉に甘えて、実母の理不尽さを訴え、自分の正当性を主張し、大泣きしたら、少しは楽になったのかもしれない。
けれど絶対に私は泣いちゃいけなかった。
そんな楽をしてはいけないと思った。
先輩が言ってくれたように、実母が表出した怒りも憎しみも、きっと私に対してのものじゃない。
娘を奪おうとしている病気に対してのやりきれない思いが医療者に対するものに転化されてしまっているだけ。
まだ経験が浅く、おどおどと自信なく病室に入り、けれど懸命に看護する私に、苛立ちをぶつけてしまっただけ。
けれど、そんなことは関係がなかった。
実母の言葉はまさに私が私に対して思っていることだったのだ。
まざまざと家族に事実を突きつけられて、見ないことにしていた自分の無力さに打ちのめされた。
私にはなにもできない。
わたしにできたのは、ただただ、身体を拭いたり、排泄のお手伝いをしたり、着替えを手伝ったりすることだけ。
呼吸が苦しい彼女にとってはそれすら、苦しさを増強する拷問のような日課かもしれなくて、彼女の病室に行くのが苦痛だった。
彼女が病室で息を引き取った時、勤務でなにをしていたのか、覚えていない。
その日、彼女を受け持っていたのは私ではなかったけれど、ナースステーションに飛んでいる心電図モニターの線がまっすぐになり、心拍が0を示すのをじっと見つめていた記憶だけが鮮明に残っている。

重い重いからだを引きずるようにして帰り、夕飯もたべず、家族と会話らしい会話もろくにせず、布団にもぐりこんだ。
私があの時トイレに行かせたのがいけなかったんじゃないか。
私のケアが悪くて、死期を早めてしまったのではないか、
彼女をあの日ケアするのは、私ではいけなかったのではないか、
私なんかが、死にゆく人のケアをしていいのか、
ぐるぐると、後悔と恐ろしさと自責の念が頭の中で渦を巻き、枕に口を押し付けて泣いた。
苦しくて苦しくて、ドロドロとした感情の渦を全て吐き出したくて、嘔吐するように泣き続けた。




