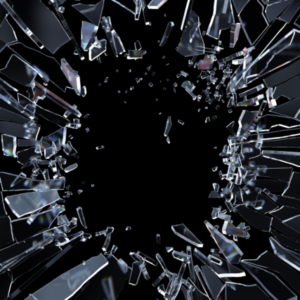大人になれば、痛みをないことにしたり、克服したりするテクニックに長けてくるし、様々なインナーワークでそこそこ自分と向き合ってきたつもりだったから、あえて痛みなんて見に行かなくても、そこそこうまく生活できていた。
だけど今私は「痛み」というものに光を当て、絡まったままの結び目をひとつひとつほどいていくような、気の遠くなる、ひどくしんどい、だけど自分とつながりなおすような大切な時間を過ごしている。
兄の死
兄の話をしようと思う。6歳離れた兄は、背が高く、スタイリッシュで、友達に囲まれ、本当にかっここいい人だった。
私が男の子にデートをすっぽかされたときには、車でおしゃれなカフェに連れて行ってくれたり、高校生の一時期、学校をサボっていると、「ほら、行くぞ!」と気まぐれに車で学校まで送ってくれたりした。
その兄が自死したのは私が23歳の時。
その日、夕方から降り出したゲリラ豪雨でびしょぬれになりそうだったから、お風呂を入れておいてもらおうと思って、珍しく仕事終わりに家に電話した。電話口から
「〇〇がー!〇〇がー!」
と兄の名前を呼ぶ、母の悲鳴のような声を聞き、職場を飛び出した。
「間に合って、間に合って」
人目もはばからず、呪文のようにそれだけを唱えながら、どうやってたどり着いたのか、気づいた時には兄が運ばれた病院の廊下にいた。
先に病院に着いていた父の
「もえ、気をしっかり持てよ」
という言葉を聞いて、間に合わなかったんだと悟った。
私は叫び、その場で倒れた。
知らない男性がふたり、後ろから私を支えてくれたけれど、それは警察の人だった。
案内された部屋の前に立つと、少しだけ空いた扉の奥から母のすすり泣きと、兄の名前を呼ぶ声が聞こえる。
少し近づくとドアの隙間から兄の足が見える。
歩くたびに、身体、腕と見える範囲が少しずつ広がってきて、最後に見えた顔には白い布がかかっていて、兄は本当に死んでいるのだと知った。
母が布をとると、眠ったような兄の顔が見える。
きれいな顔だった。何年間もまともに見ることがなかった兄の顔。
そこで記憶は一旦途切れる。
始まりはペルーだった。
旅人だった兄は、大学に通う合間に、大きなバックパックをしょって、何か月も世界中を旅していた。長旅から帰ってくるといつも日に焼けて、目がキラキラと輝き、彼の周りだけ爽やかな風が吹いているようだった。
何人もの友達が、彼の影響を受けて旅を始めた。私も兄の影響を受けて、よくひとりで旅に出るようになった。
ある年、いつものように数か月旅に出て、南米から帰ってきた兄は、また一段と自由になった様だった。東京の真ん中を、白いTシャツと綿のパンツで分厚い本だけを手にもって、少しほほ笑みながら歩くスラっとした姿は、浮世離れした美しさがあった。

そして兄の変化と私の変化
ところが、しばらく東京で日常を送っていると、人が変わったように「人間の欲」というものをすべて否定するようになり、世の中に対する怒りを攻撃的に表現するようになった。
人間の欲が地球を、世界をこんな風にしてしまったと、どうしよもないことに本気で怒りを表出していた。
兄にももちろん食欲や睡眠欲はある。
その欲を否定するように、まるで苦行僧のような水も唾液も飲まないような断食や、座禅(時折うなり声をあげる)を始め、プラスティックのごみは目に入れば全て拾ってきてしまうようになった。
水を大量に使うことも悪の所業だから、お風呂にも入らないのでひどいにおいを発する。
文明を否定しているから、大学にも行かなくなり、一日中家で座禅を組んでいる。
その座禅は実家の居間で行っていたから、私は否が応でも、毎日何度もそのにおいをかがなければいけない。(うちは居間を通らないと台所にも、お風呂にも行けない構造だった。)
コンビニに寄って帰れば、人を殺してきたかのように批判され、
「それでいいのか?そんな生き方でいいのか?」
と詰め寄られる。
ペルーで何があったのかを聞いても、
「お前にはわからない。言う意味はない」
と突き放される。
20台前半の私は、変化した、鬼気迫った、臭い兄を受け入れられなかった。
両親はその頃、傾いた会社を立て直すのに必死で働いていてほとんど家にいなかったし、もう一人の兄は司法修習で九州にいた。
逃げ場がない。
そのうち私は狂ったように兄を罵倒するようになった。
「死ね!」
と罵ったし、家で修行するなら出家しろ、と本気で思っていた。
私がこんなにも人を憎めるなんて知らなかった。
私がこんなにも毒のある言葉を人に対して吐けるなんて知らなかった。
兄を見る度に私の一番攻撃的な、一番醜い、一番毒々しい部分が刺激され、泣きながら罵った。
兄を傷つけるためのありとあらゆる言葉を使った。
完全な拒絶
そのうち、私は兄を見ると体中に蕁麻疹が出るようになった。
体からの拒絶だった。
変わっていく私を見た両親が、兄と私が一緒にいない方がいいと判断し、それからしばらくはキャリーケースであちらこちらのウィークリーマンションを点々とした。
ウィークリーマンションの契約が切れる日には、またキャリーケースに荷物を全部いれて、学校に行き、学校帰りに新しいウィークリーマンションのカギをもらってそのまま移動した。
数か月たっても私の症状はよくならなかったし、兄に対する拒絶は決定的だった。
私は本格的に一人暮らしを始め、学校を卒業するまでそれは続いた。
その頃の兄がどう過ごしていたか、私はほとんど知らない。断食があまりに長く続き、命が危なくなり、病院に無理やり入院させたりもしたようだ。
九州から帰った下の兄が泣きながら、朦朧とした兄の口にスプーンで水を運んだとも聞いた。
再び穏やかさを取り戻す
私が卒業し、実家に戻った頃には一見全部が穏やかに、落ち着いているように見えた。
けれど、一度決定的に傷つけあい、切れてしまった関係は簡単には戻らない。私と兄はお互い会わないように注意深く過ごしていた。
同じ屋根の下で暮らしている中で、穏やかな人に戻っていた兄と少しは成長した私。
そのうちドア越しに少しだけ話すようになった。
「ごはんできてるよ」とか、「荷物が届いてるよ。」とかそんな言葉。
兄はドアの向こうから「あ~」とか「うん」とか答える。
元通りの関係とはいかなくても、こんな風に少しずつ時間が、優しい気持ちをお互いに持てるようにしてくれるんだと思っていた。いつかまたお兄ちゃんと話す日も来るはずだった。
そして前日。
テレビを居間で見ていたら、スーッと兄が入ってきた。ありえないことだ。
「どうしたの?」
と聞くと、私の顔を見て
「うん」
と言った。そして静かに自室に帰っていった。私はまたテレビを見た。
翌日の夕方、兄は死んだ。
お別れだった。
あの「うん」はお別れだったのだ。
兄は死んだ 記憶の断片をつなぎ合わせてみる
病院の次の記憶は自宅で警察の人が状況検分をしているところ。
植木用のはさみとロープの切れ端が生々しく転がっていた。(そのあと数年間、ひも状のものを見ると動機が止まらなくなった)
想像と事実が交錯する。
兄が静かに準備をする姿が思い浮かぶ。
隣の家との目隠し。
足代になる椅子を準備するところ。
最後の一歩を踏み出すその瞬間。
母が見つけて、狂ったような悲鳴をあげ、兄にしがみつく。
小さな身体で180㎝の兄を下す。
兄の名前を何度も何度も叫ぶ。
私がかけた電話が鳴る。
警察署にも行った。
一晩兄は警察で過ごすのだという。ちゃんと兄の周りにお線香やろうそくがともされていた。
自宅に帰ると、父さん、母さん、二番目の兄、私は一つの部屋で並んで手をつないで眠った。
繰り返す浅い眠りの中、明け方に夢を見た。
死んでいるはずの兄がいて、背後に大きな山が見える。
私は聞く。
「お兄ちゃん、お兄ちゃん、会いたいよ。どうやったら会えるの?」
兄は答える。
「天を見上げて両手を広げたら会えるよ」
数か月後、お墓参りに来てくれた、兄の旅仲間が、兄がペルーでシャーマンの儀式に参加したことを教えてくれた。まだだれもアヤワスカなんて言葉を知らなかった頃。その言葉はずっと私の脳裏に刻まれることになる。
あぁ、あの夢の中の山はペルーの山なのだとおもった。

そのあと、何度も何度も天を見上げて両手を広げてみている。
伝えていないことが多すぎた。時間が解決してくれると何となく思っていた。
生きているだけでいい。息しているだけでいい。
命があればそれでいい。
若い私は、そのことに気づいていなかった。どんなに罵りあったとしても、私にとって兄は大切な人だった。そのことに私は気づいていなかった。
続く